絶滅危惧種?年賀状はこの先どうなるのか
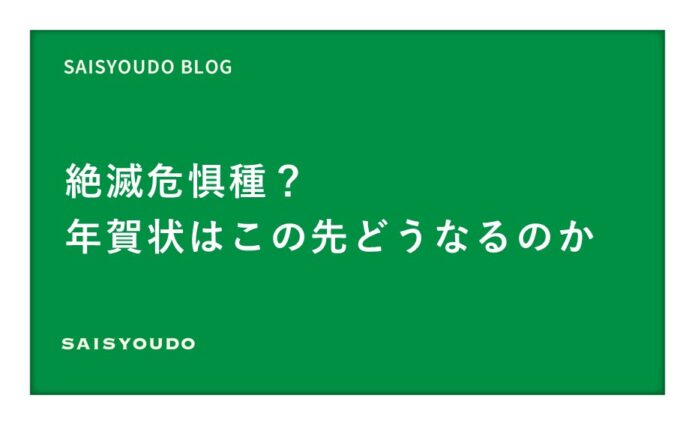
年賀状発行枚数の推移
年賀はがきは1949年に初めて発行され、当時は1億8000万枚でした。その後の高度経済成長期を背景に発行枚数は増加し続け、1964年には10億枚、1973年には20億枚を突破。ピークは2003年で44.6億枚に達しました。
しかしその後は減少が続き、直近2025年用は10.7億枚と前年から25.7%減少。ピーク時の4分の1以下まで落ち込んでいます。過去16年間、すべて前年比マイナスという厳しい状況です。
この数字だけを見ても、年賀状が「絶滅危惧種」と呼べるほどの存在になってきたことが分かります。
代替品の脅威
背景には人口減少もありますが、より大きな要因は「代替品の脅威」です。マイケル・ポーターのファイブフォースモデルにおける代替品とは、既存の商品やサービスを置き換える新たな手段を指します。
年賀状の場合、それはメール、SNS、LINEなどです。これらは低コストで即時性があり、双方向のやり取りが可能。従来、紙の年賀状が担っていた「新年の挨拶」「旧年中の感謝」「疎遠になった人との再接続」「ビジネス上の礼儀」などの役割は、いまやデジタルで簡単に代替できるようになりました。
弊社が年賀状を廃止した理由
弊社も数年前に年賀状の送付を廃止しました。その背景には二つの理由があります。
第一に、得意先からの年賀状印刷受注が減少し続ける中で、自社だけが年賀状を出し続けることに疑問を抱いたためです。市場が「不要」というサインを出している中で、あえて逆行する必要はないと判断しました。
第二に、年賀状印刷の効率の問題です。なぜか4丁判しかなく、3mmの余白もないため塗り足しデザインがしにくい。とはいえ、オンデマンド印刷との相性は良い分野です。宛名は1枚ごとに異なり、複数絵柄や可変デザインにも対応できる。技術的にはむしろオンデマンドの強みを発揮できる領域でした。しかし残念ながら、需要そのものが縮小している現実には抗えません。数字がそれを物語っています。
新しい仕組みの登場
一方で、工夫の余地がまったくないわけではありません。富士フイルムイメージングシステムズが展開する「Web年賀状サービス(Webpo)」のように、住所を知らない相手にも紙の年賀状を送れる仕組みが存在します。
実はこのサービス自体は2013年から提供されていましたが、気がつけば富士フイルムが手掛けていたのは驚きでした。「いつの間に!?」と思った方も多いのではないでしょうか。
URL: 富士フイルムイメージングシステムズ Webpo
このような仕組みはネットワーク外部性に依存せずに需要を掘り起こす可能性を秘めています。ただし同時に「そもそも紙で受け取る意味はあるのか」という根本的な問いも突き付けられています。
今後の可能性
日本国内で年賀状の需要が再び拡大する可能性は低いでしょう。人口減少とデジタル化の加速を考えると、規模縮小は避けられません。むしろ、日本独自の「紙の挨拶文化」を海外に広めることの方が現実的な可能性かもしれません。
年賀状は単なる通信手段ではなく、相手を思いやる気持ちを形にする文化資産です。その価値を再定義し、新しい場で生かすことができれば、違った形で生き残る道も見えてくるでしょう。
印刷業界にとって年賀状の衰退は確かに脅威です。しかし同時に、新しい価値を提案するチャンスでもあります。伝統を尊重しつつ、デジタル時代に適応した「紙の活かし方」を模索することこそ、これからの鍵になるはずです。





